
はあ、はあ、はあ。
美琴は荒い息にさいなまれていた。
心臓が体内で暴れている。
たぶん、そこはキャビンだ。ソファに横たわっている。
なぜだか、ひざをたてていた。
湿った音がしている。
なんだろう。
この音はなんだろう。
それに、どうしてこんなに暑いのか。
室温が高いから、だけではない。
自分自身が熱くなっているのだ。
美琴は指の先にうるみを感じる。
そうだ。
ここはたしか助平のヨットで――
美琴は水着の上から自分の恥ずかしい部分を――
恥ずかしいところを見てほしくて――
さわっていた。
たぶん、水着の股ぐりの部分が密着して、形がはっきり見えているのではないか。
生まれてから一度も――おしめをしていた時期をのぞけば――だれにも見せたことのない部分が。
すごくエッチな気分だった。こんなのいままでなかった。
指がとまらない。
「あんっ、あっ、はあ……」
声がこらえられない。
どうしてこんなに気持ちがいいのか。
助平のせいだ、と思った。
大人びた風貌。ふかい知性を感じさせる目許。バランスのよい鼻と唇。男らしさを秘めた顎から喉、鎖骨から肩の盛りあがりにつながるライン。
助平に会うまで、オナニーだってしたことがなかったほどなのに。
「助平さん……おねがい……きて……」
抱いてほしい。助平に犯されたい。それが美琴の願い。
助平が近づく。
体温がつたわる。助平に体臭はない。安っぽいコロンなどさらに似合わない。不思議な芳香と海のにおい。それこそが助平にふさわしい。
美琴は唇をかすかにひらき、助平の口づけを受けとめる。
なんのためらいもなく舌が侵入し、美琴の脳髄をしびれさせる。
こうしてほしかった。ずっと、こうしてほしかった。
「助平さん、すき……」
美琴は幸福の波に翻弄されながら、自ら水着の布をめくり、少女の部分を露出させた。
その部分はもうじゅうぶんに潤っている。
処女の花びらは愛のほとばしりに濡れ、男の暴慢な侵入を待ち受けている。期待にふるえながら。
入ってくる。
入って……
「あうっ……うあああ……」
美琴はわななく。
***
「――たしかな情報か」
助平は操縦席にいた。
表情は暗い。
通信機が意味不明の叫びをもらす。
助平はうなずいた。彼には意味がわかるのだ。
「やむをえない。実験規模は縮小する。このままではこの場所も発見されるだろう」
通信機が心配げな女の声でひとしきり鳴る。
「わかっている。やつらがイニシアチブをとれば、この世界もほかのところと同じように塗りつぶされてしまう。そんなことはさせられない。ちょうど周期もめぐってきたところだ。実験は充分ではないが、試すしかない……」
通信機をオフにする。
キャビンのほうに目をやる。
愛らしい少女がソファの上で自慰にふけっている。無我夢中のようだ。
たどたどしく指で股間を刺激しながら、切ない声をたてている。
ふだんからオナニーそのものをしつけていないのだろう。ワレメの上をなんとなくこすっているだけだ。それでも刺激的なのか、激しくあえいでいる。
熟す前の果実にも似た処女の性臭がただよっている。
「助平さあん、ひろひらさ……ああんっ、おねがいい……」
砂糖菓子のような声で求めている。
助平は立ちあがり、ソファのほうに歩みよっていく。その表情は、複雑だ。
「あーっ、気持ち、いいっ!」
真由美は全身をつらぬく快楽に身もだえた。
大きなものが、真由美の中をこすりあげ、ひきずりだそうとしているようだ。
アヌスに、入れられている。
深く、奥まで、つらぬかれている。
「おしりがあついよおっ」
この感覚はくせになりそうだった。いや、もうなってしまっているのかもしれない。
はじめてそれを体験したのは、子供のとき。
好男との秘められた遊び。
そのころからエッチだった好男は、おさない真由美の肛門をいじっていた。ぴったりと閉じたあそこにはさほど興味はないようだった。
それに、子供のころはそんな場所では快感はあまり感じない。
子供はおしりが好きなのだ。
よしおちゃんはどうしてあんなにエッチなのかな。
そう思いつつも、お医者さんごっこをねだる好男をこばむことができない。
むろん、そのかわり、柔道ごっこにつきあってもらう。
一本背負い、袈裟がため、上四方がため、裸じめ。
そういった荒業をかけていっても、あとでお医者さんごっこという「ごほうび」があるときの好男はぜんぜん参ったをしない。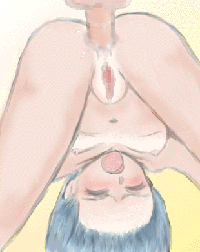
真由美は技をかけながら、どきどきしている。そのあとのことに、幼いながらも、期待しているのだ。
「じゃあ、まゆみちゃん、ぼくが先生だからね」
顔に青タンをつくって、自分が患者をやったほうが似合うだろうに、好男はしかつめらしく宣言する。
「わかったわよお」
「じゃあ、パンツぬいで」
「うん……」
スカートはきらいだ。男の子のような半ズボンが好き。
ズボンとパンツを脱いで、好男の前に立つ。
「じゃあ、検査しまあす」
指で、ワレメをかきわける。
恥垢が指につく。においをかぐ好男。顔をしかめる。
「くさーい」
「やだ……」
今晩、お風呂でちゃんと洗おう、と決意する。
「じゃあ、こんどはおしりを調べまあす。うしろをむいてくださあい」
「う〜ん」
無防備に裸のおしりを好男にむけるのは気がひける。
でも、しょうがない。そういう遊びなのだから。それに、好男にすべてを見せるのはいやじゃない。
真由美はつるんとしたおしりを好男の目の前にさらす。
「もっとだしてくださあい」
「こう?」
「もっと」
「こう……?」
ほとんど上体を曲げておしりだけを突き出している。
「すごい……まゆみちゃんのおしりのアナ、ひらいてるよ」
「うそ……うそぉ……」
「ほんとだよ。ほうら」
手で、おしりの山を左右にひらく。
にゅちゃ、と音がして、真由美の肛門が外気にさらされる感じがする。
「ぱくばくしてる……」
「やだあ……あんまりしないでえ」
真由美はおしりを振っていやいやをする。
「だめだよ、これから浣腸するんだから」
「ええっ、するのぉ?」
「だって、約束したじゃないかあ。体落とし十回で浣腸一回って」
たしかに、した。ちなみに体落としは十二回かました。
「あれ、痛いんだもん」
「体落としのほうが痛いよっ!」
そのとおりだ。それに、好男にくらわせたのは体落としだけではない。
「……わかったわよお」
真由美はしぶしぶみとめる。ドキドキがつのる。アレをされるのだ。
「行くよ……」
さすがに好男の声も緊張している。人差し指をつばで湿らせ、じりじりと真由美のヒップに近づける。
その部分にふれる。
「あっ……」
真由美の背筋にぞぞっと戦慄がはしる。アレ、されちゃう。
ぐうっ。
「ああっ……」
ぬぐうっ。
「ひいいっ!」
おしりに、ふとくて固いものが入っている。
指を動かすよ、まゆみちゃん……
好男の声が聞こえる。真由美は夢中でうなずいている。
いや、いや……いやだけど……キモチいい……。
それが、真由美にとっての初めてなのだ。その感覚がいま、ありありと蘇っていた。
オチンチンを入れちゃったよ、まゆみちゃん……奥まではいってるよ……
好男がそう言っているような気がする。でも、そんなはずない。
好男は指しか入れなかった。ペニスを入れるなんてことは考えもしなかった。
だから、これは錯覚だ。夢だ。
でも、いま真由美のおしりに入っているものは――夢じゃない。
アヌスにペニスが押しこまれるごとに、膣に射精された粘液が圧迫されて、噴き出している。
ぶぴゅ、ぴゅう、と鳴っている。
子宮が、共鳴している。
女のからだは楽器に似ている。
男根が貫き、粘膜同士を触れあわせながら擦りあげるとき、女の器官が鳴りひびく。快楽のうたをうたう。
真由美は一個の楽器だった。
これが、生きているということなのだ。
「死んじゃうっ、死んじゃううッ!」
そう叫びつつ、真っ白い世界を見ていた。矛盾のなかに、真実はある。
粘膜を犯される嫌悪は快感を増幅させ、死をイメージさせる切迫感はまさに生命の真髄を垣間見せる。
嘘がほんとうになり、真実が虚構になる。
真由美はおしりを衝きあげた。意識がスパークしている。
もう、だれの男根でもよかった。すべてを受け入れたい、注ぎ込まれたい、そう思った。
静香は目をひらいた。
二十何人めかの男が静香のなかで動いていた。
あれから――海の家のシャワー室で見知らぬおやじどもに犯されてから――静香の身体についた炎はおさまらなかった。海のにおい、潮騒が性欲をどんどん汲みあげた。
男たちも静香をもとめた。
モラルは消えうせていた。
静香だけではなかったのだ。
みんな、なにかに狂っていた。あちこちで人々はまぐわっていた。
静香も乞われるままに股をひらいた。たちまち身体中が精液にまみれた。そのにおいにさらに興奮が高まった。
いつまでもこの宴が続けばいい、そう思った。
これが本来の人間の姿なのだ。自然のなかで、男も女もけだものになる。たがいを求めあい、むさぼりあう。そして、与えあいもする。
そうすれば、すべてがうまくいく。
服を着るから、決まりごとをつくるから、あらそいがはじまるのだ。
ネクタイをしめて、スーツに身をかためて、人はおのれを檻にとじこめる。外からの攻撃にそなえることで、ほんとうの自分を押し隠してしまうのだ。
生きるために必要な、そう、こんな気持ちいいことをするために、いろいろな手順を踏まなくてはならない。控えめな誘い、どうとでもとれる言い回し、それは拒絶されたときの心の傷をできるだけ小さくするための保険。もどかしいやりとり、儀礼的なデート、何度目からキス? それはそれで楽しいけれど、でも、まどろっこしい。
必要としているもの同士で気軽に交われたら、それがそれでいちばんよいこと。
そのためのサインをほんとうは人間は持っているのに。
フェロモン。性のしるし。たがいに惹かれあい、ひとつになるのに、なんの制限が必要なのだろう。結婚制度? 戸籍? 世間体? 慎み、節度、くだらない。
こすりつけあう粘膜の間で交わされる会話こそが、生きているものにとって重要なことなのだ。
それが、そのことが静香には痛いほど、いや気持ちいいほどにわかった。
だから、どんな醜い男の求めにも応じた。口をつかい、指をつかい、股間を、おしりを使った。あらゆる場所で射精を導き、熱い性のシャワーをあびた。
いまもだ。四十代とみえる中年男が少年のように頬をそめて、静香の肉体をむさぼっている。
動きが性急になっていく。のぼりつめていく。
饗宴が、祭が――
――終わりなの?
男が射精した。静香のなかを熱いものが満たしていく。だが、それは今までの弾けるようなほとばしりではなく――
静香は青い空を見ていた。風にまじる匂いの質が変化したように思った。
潮がとおのいていく。白い砂浜がどこまでもつづいている。
男が身体を起こした。熱狂はすでになく、冷え冷えとした表情をまとっている。静香の姿も目に入らないかのように自分の身仕度だけを整えはじめる。
静香の目尻に涙がうかんだ。オルガスムスの余韻のためなのか、それとも、自分のなかを駆けぬけたものを惜しんだのか。
自分でもわからなかった。
そしてわからないままに、記憶がホワイトアウトしていった。
「ああ〜、つかれたあ」
真由美が水着姿のまま、デッキチェアに腰をしずめた。
そのおでこを好男がつっついた。
「なんだよ、おばはんくせー」
「なによー、だいたい、どこ行ってたのよ!? あんたを探し回って、けっきょく陽が暮れちゃったじゃないよ!」
つっついた好男の指をつかんで、真由美は逆に極める。好男は絶叫。
水平線に夕陽が沈みかけている。
「それにしてもすごいヨットねえ、先生、びっくりしちゃった」
さすがにきわどい水着で生徒の前に立つのはまずいと思ってか、パーカーを羽織った中条静香教諭がヨットの造りに感嘆の声をあげる。
「ちょっとしたナイトクルージングには最適でしょう」
助平が操縦室から笑みを含んだ声をかえす。
槍倒島が小さく見えている。ヨットは島から離れるコースをとっている。
「でも……ちょっと遠すぎない?」
かすかに心配がきざしたのか、静香は眉根をくもらせた。
助平は操縦システムをしめす。
「平気ですよ。人工衛星をつかったガイドシステムによるオートパイロットですから」
「ふうん……」
静香はわからないままにうなずいた。機械にはまったくうといのだ。
「でも、大河原さんじゃないけど、すごく疲れたわ。なんだかものすごい運動をしたみたい」
おおあくびをする。その拍子に大きな胸がぷるんとゆれる。
「ああ〜、美琴、こんなとこで寝てるう」
真由美がキャビンのなかをのぞきこんで大声をあげる。
ソファに横たわっている美琴の側に駆けよる。
美琴の身体にはタオルケットがかけられている。かぜをひかないように、という助平の配慮だろう。
「なんか、幸せそう……」
美琴の寝顔をみて、真由美は言った。
「すごくいい夢、みてるんだろうな」
「それはよいとして……はなしてくれよ……」
まだ指を極められたままの好男がくぐもった声をだす。
真由美はこわい顔をして好男をにらんだ。
「だめ。あんたは今日の罰をくれてやらなきゃ。せっかくの午後がだいなしになったんだからね」
「なんだよお、おまえだってどっかで遊んでたんだろお?」
「遊ぶったって……だって……」
真由美はふと考えこむ様子をみせた。
「なにしてたんだろ、あたし、陽が暮れるまで」
そのときだ。静香が後部デッキから大声をあげた。
「すごいわよお、島のほう! 花火かしらあ!?」
真由美と好男は小競り合いも忘れて、キャビンから駆け出した。
「うわっ」
「すごーいっ」
夜空に七色の光がとびかっていた。
青白い光の球がいくつも島の上空にあらわれ、そして島の輪郭を照らし出した。
「まるでUFOみたいっ!」
真由美がはしゃいだ声をあげた時だ。
島が巨大な光におおわれた。その光は完全に島をのみこみ――そして消えた。
「島が――きえた」
好男が惚けたような声をもらした。
その声を背に、助平は顔すら動かさなかった。
まっすぐ前を見つめている。
ヨットは、東京を目指し、まっすぐに進んでいた。
海洋リゾートのメッカ、槍倒島の名前は、その後、どんな観光ガイドブックにも見いだせなかった。地図にも存在しない。行ったことがあるという人間もいない。
そんなふうにして、1999年の夏休みは終わった。