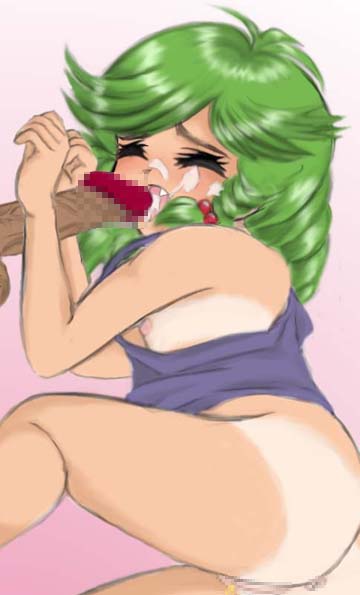
◇「チンチンをしゃぶらせる」を選択
美耶子の懇願におれはニターリと笑った。おれのなかの悪魔が目を覚ましてしまったのだ。ああ、なんということだろう。
こうなってしまうと、おれは悪魔の言うなりになるしかないのだ。おれは、心にもない要求を美耶子に対して出した。
「口だけじゃないところを見せてもらおうじゃないか、美耶子。トイレに行かせてほしかったら、おれのチンチンをしゃぶってみろ」
「ええ、はあ、なに?」
美耶子はさっきから太股をもぞもぞさせている。催して催してしょうがないのだ。おれが――いや、おれのなかの悪魔が言った内容さえ、よく理解していないようだ。
「だから、おれのチンチンをしゃぶったら、トイレに行かせてやる」
「ち、ちんちん……?」
美耶子は苦しげに眉をしかめながら、その言葉を口にした。
「ど、どうして……そんな……」
「やりたくなければ、べつにいいぜ。ここでゆっくり話でもしようや」
おれは美耶子のお腹を手で圧した。
「うあああっ、しゃ、しゃぶるっ、しゃぶるからあっ」
美耶子は髪を振り乱して声を放った。
「はやくっ、オチンチン出してよっ!」
「おおこわ」
すごい剣幕だ。
おれが取り出したペニスを見ても、どうということはないらしい。もう顔色がまっさおで、カタカタ震えている。
「はやく、はやくっ」
そんなにせかされても、と思うが、美耶子はべつにフェラチオをしたいのではなく、とっととトイレに行きたいだけなのだ。
その行為の意味さえ、ほんとのところはわかっていないだろう。
でも、生意気な美耶子にチンチンをしゃぶらせることを想像しただけで、不肖のムスコはピンピンになってしまっている。自分を信じられなくなるなあ、おれ。
そそり立ったものを美耶子の顔の前に出した。
「ど、どうするのっ」
美耶子は明らかに切迫している。口調に余裕がない。ほんとうになんでもやりそうだ。
「アイスキャンデーを舐めるように、吸いこんで、舌をからめたりせよ」
「わかったっ」
美耶子は唇をひらいた。
その歯並びを見て、おれはちょっとばかりいやな予感がした。
美耶子ってば、八重歯だったかもしれん。それも、かなり鋭いキバを持っていたような。
「あたっ、あたあたあたっ」
ケンシロウではない。おれだ。
「こらっ、美耶子、歯を立てるな」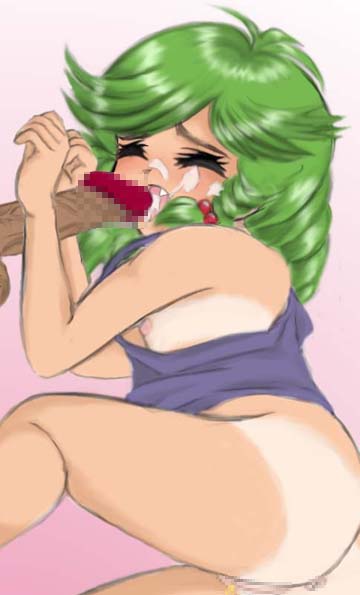
「ほんはほほひっはっへ……ぷはっ、これでいいでしょ、トイレに行かせてっ」
「一瞬、くわえただけじゃだめだっ! もっとちゃんと舐めたり吸ったりしろ」
「そんなこと言ったって……もおっ!」
文句を言っても、おれが放しそうにないことを悟ったのだろう。美耶子はおれのチンチンを再びくわえた。
「歯を立てるな……そう、そこを舐めてくれ。ペロペロと……あ……お……いいかも」
「ふぐぅ、ふごお」
美耶子はこらえている。こらえながら、舌を動かしている。鼻息がおれの陰毛をゆらしている。
「奥まで吸いこむんだ、そうら」
美耶子の喉に、ぐいぐいと押し込んでいく。ああ、おれって悪魔。
「むううッ、ふびいッ」
おれは美耶子の顔をおさえ、チンチンの先で、ほっぺの内側をグリグリしてやる。美耶子の輪郭が変わる。じゅるじゅると美耶子の口腔が唾液で満たされていく。小さな舌が亀頭のくびれのところにからみつく。いけね、出ちまう。
「あっ、あっ、ううっ」
おれは腰を引いた。どろっとした粘液がおれの奥から噴出してくる。すごい快感だ。
熱くてトロトロの精液が美耶子の顔にたっぷりと注がれる。
「ひあっ!」
さすがに驚いたのか、美耶子がのけぞる。そのショックで、括約筋がゆるんだのか。
「あっ、ひああ……だめえっ」
しゃわっ。
熱いしぶきがおれの体にもかかった。おしっこだ。
「も……もれちゃったあ……」
美耶子は半泣きだ。
さすがに、もう余裕はない。おれはあわてて美耶子を抱きかかえて便所に走った。
***
「あら、遊一さん、お掃除ですか?」
買い物から帰ってきた一子ちゃんが驚いたように声をかけてきた。
「わざわざ廊下をぞうきんがけまでしていただいて――どうかしたのですか?」
「いやあ……ははは」
おれは縁側に膝をつき、バケツのなかでぞうきんをゆすぎながら、顔をゆがめた。
「とっとと続きをなさい、遊一っ!」
美耶子がおれの背中を蹴った。
「まあ、なんですか、美耶子!」
一子ちゃんが柳眉を逆立てかけるのをおれはあわてて止めた。ここで一子ちゃんが美耶子を叱りつけたりしたら、それはまわりまわっておれの頭上で炸裂することになる。
「ちょっとしたゲームを美耶子ちゃんとして――そう、これは罰ゲームなんですよ、あっははは」
「そうだよ。今後は、遊一はあたしのことをなんでも聞くことになったの。つまり、下僕ね」
ぺちぺちとおれの頭を張る。おれは怒鳴りつけたいのをぐっとガマンする。
「――はあ」
一子ちゃんは目を丸くしている。おれがあまりに不甲斐ないのであきれたのだろうか。
いつか、仕返ししてやる――そう心に誓いながらも、おれは笑顔を浮かべつづけていた。