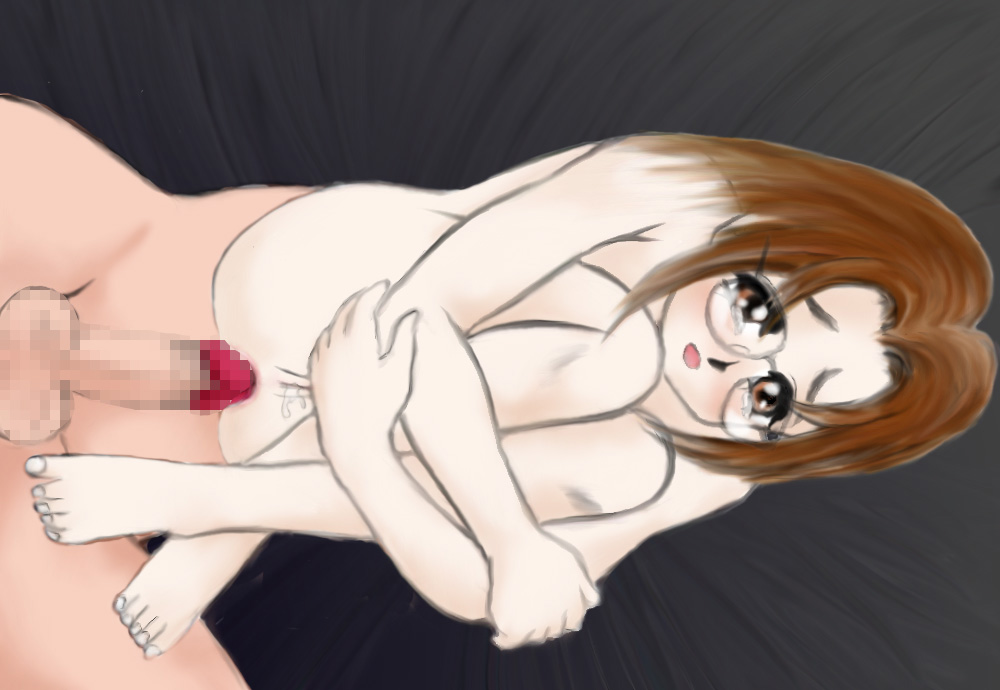
|
|
|
|
|
|
|
どうせあと一年の命だスペシャル! |
宇多方家の年少組はわりと宵っ張りだ。
姉妹のなかだと最年長の一子ちゃんが最初に脱落する。夕食の片づけが終わり、一息つくと、茶の間でテレビを見ながらもうこっくりこっくり始める。日々の家事労働の疲れからか、それとも「ほけー」としたキャラからか――たぶん後者だろう――たいていは午後十時になるかならないかで眠りこんでしまう。
気恵くんは夕食がすむとすぐに自分の部屋にひっこんでしまうので、何時まで起きているのかはさだかではない。が、電灯が消えるのはだいたい午前零時すぎであるようだ。まだ受験には間があるが、こもって勉強しているみたいである。
一子ちゃん脱落の時点で、宇多方家の茶の間にはおれと苑子と美耶子・珠子が残っている。もっとも珠子の場合は霊界通信をしていることが多いので、肉体が茶の間にあっても精神は別のアストラル界かどっかに飛んでおり勘定には入らない。
美耶子は明確に夜型らしい。猫のような眼が、夜が更けるごとにらんらんと輝いてくるようだ。深夜番組を食い入るように見つめているかと思うと、ささいなことでおれにからんできたりする。
逆に、苑子はおとなしい。苑子のほうが美耶子よりもふたつほど年上なのだが、引っ込み思案な性格なためか、お姉さんらしい振る舞いというのはあまり見せない。が、夜にはそれなりに強いようで、眼鏡の奥のくりっとした目をしょぼつかせることもなく、だいたい最後のお開きの時まで居残っている。
その夜も、ほぼ、いつもと同じ展開だった。
気恵くんは自室にこもり、一子ちゃんは畳に顔を押し当てて、幸せそうに寝息をたてている。あれだとほっぺたに跡が残るよなあ……べつにいいか。
珠子は例によって姿が見えない。また新たな霊体でもキャッチしたのかもしれない。
テレビはくっだらないお笑い番組を流している。おれとしては裏番組のトゥナイト――ムフフ風俗特集とかを見たいのだが、このメンバーでその番組を視聴しようと呼びかけるのは気がひけるので、そのまま惰性で画面をながめていた。
苑子はおれの隣にちょこんと腰をおろして、テレビの画面を真剣に見つめている。
「あー、また、苑子ちゃんてば、ゆーいちにくっついてるー」
夜になるとナチュラル・ハイになるらしい美耶子が声をあげつつ、おれと苑子の間に割って入ってきた。
「だめだーめ。ゆーいちのバカがうつっちゃうよーう、苑子ちゃん」
美耶子はおれの頭をぺちぺち叩く。こん、ガキが。復讐すべく、おれは美耶子のスカートを無言でまくった。むろん、その下はお子さま白パンツだ。
「ぎゃあ! エッチ、スケベ、ヘンタイ!」
わざとらしく悲鳴をあげ、美耶子がキックをかましてくる。おれはその細い脚をむんずと捉えると、美耶子の軽い身体を持ちあげて、畳の上に転がした。スカートが思いっきりめくれあがるが、めげずに美耶子が下から蹴りあげてくる。
それにかまわず、おれは美耶子の両足首をつかむと、大きく左右に股を割った。
「必殺、電気あんまじゃい!」
美耶子のまたぐらに足を入れて、震動を送りこむ。
「ひゃああああっ! やめろぉぉぉ!」
笑いの発作に衝き動かされるように、美耶子が引きつった声をあげる。
おれはさらに激しく足を動かす。白パンツの股の、食い込んでいる縦じわの部分を集中的に、こう、ぐりぐりぐり、と。
「ひいいっ、ギブ、ギブぅ〜」
美耶子がタップアウトする。
――えーと。ちょっとだけ補足させてくれ。
これは「無邪気なプロレスごっこ」だぞ。それも美耶子の方から仕掛けてきたのであって、おれはそれに乗ってやっただけだ。いいから信じろ。
「ふふん、口ほどにもない」
おれはうそぶき、また元の姿勢にもどる。
美耶子はすぐさま起き直って、体当たりをかましてくる。
しかたなく、おれは美耶子の身体を抱きかかえて、その行動を封じる。
「えーい、だまってテレビでも見てろ」
膝の上にむりやり座らせる。
「やだやだ、ゆーいちの手、おっぱいさわってる、ヘンタイっ!」
「ばかたれ。どこにおっぱいがあるっちゅーんじゃ。ぺったんこのくせに」
おれは美耶子の胸のあたりを手でまさぐるふりをする。まあ、実際に触っているのだが。むろん、本人が主張するような「おっぱい」的なふくらみはほとんどありしない。まあ、シャツごしに乳首が尖っているのはわかるけどな。
「ふんだ。いまに一子ねーちゃんみたいになるもん」
美耶子が唇をとがらせる。たしかに、いま、無防備にねこけている一子ちゃんの胸は年相応に立派だ。最近、またちょっと大きくなったようだし。
「おまえはずっとこのままだ、こ、の、ま、ま!」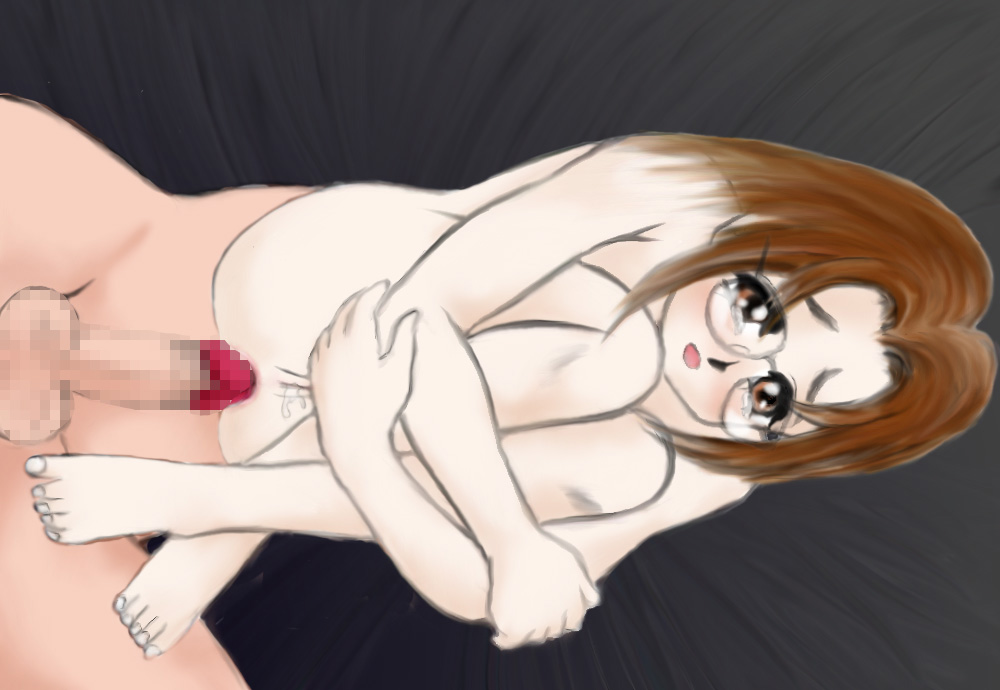
「あー、乳首つまんだ! しんじらんない、ゆーいちのどすけべ!」
怒り笑いは美耶子の機嫌がよい証拠だ。こうしてじゃれついてくるのをなんとかいなすのが、おれの夜の日課だとも言える。
なんとかおとなしくなった美耶子を膝の上に座らせていると、ぴと、と苑子が身体をよせてきた。美耶子よりも少し年嵩なぶん、まるみを帯びた身体の感触は、ちょっと触れているだけでもずいぶんとやすらぐ感じがする。
苑子は無言でテレビ画面を見つめながら、おれに体重をあずけてくる。
脇腹に、ふにっとした感触がある。苑子の胸だ。
苑子の胸は年齢のわりに大きい。たぶんあと数年で、一子ちゃんよりもグラマーになるだろう。
おれの視線に、苑子がピクンと身体を震わせる。おれを見あげながら、きゅ、としがみつくようにしてくる。胸が、完全に当たる。押しつけられてくる。
くらっ、とおれの理性が軸を失なう。おれは無意識に手を伸ばしていた。
苑子の脇の下に手をくぐらせて、パジャマごしに――ふくらみを握りしめた。
ふわふわの感触だ。掌に力を入れると、苑子の身体がぐらぐらと傾ぐ。
眼鏡の奥の大きな眼がとろんとしている。
やばい……大きくなってきちまった。
「あれえ?」
美耶子がおれの膝の上でもぞもぞおしりを動かしはじめた。
「なんか、硬いのが当たってるよお」
白パンツのヒップを直接おれの股間に押しつけてくる。
「いやらし。あたしのおっぱい触ってコーフンしたんだ? やっぱり、ゆーいちってヘンタイだぁ」
言いつつ、恥骨のあたりをこすりつけてくるんじゃないっ、ばかたりがっ。
「えーい、やめれっ」
おれは美耶子を膝の上から追いやり、立ちあがる。すまんが、心なしか前かがみだ。
「しょんべんしてくる」
「わかったー、トイレで抜いてくるんでしょ、不潔ぅ」
「ばかたれ、ちがうわ」
最近のガキはそーゆー用語だけには精通していやがる――シャレじゃねーぞ。
さすがの宵っぱり軍団も深夜一時を過ぎると元気がなくなってくる。
美耶子も、あぐらをかいたおれの腿を枕がわりに、うつらうつらし始めている。
「おーい、寝るんなら自分の部屋にいけ」
「んー、だっこしてつれてって……」
「自分で行けるだろ? ほら、ほら」
優しくするとつけあがること必至なので、おれは邪険に追いやった。
あくびしいしい立ちあがる美耶子の側に、パジャマ姿の珠子がすうっと現れて寄り添った。
「おわっ、珠子、どっからわいた!?」
もしかしたら部屋の隅にずっといたのかもしれないが、まったく気づかなかった。
珠子はめずらしくおれの方を向いたかと思うと、ふにゃふにゃの美耶子を支えながら、そのおとがいに指をかけた。
「ゆーいちおにーちゃん、おやすみなさい」
かん高い声とともに美耶子の口がぱくぱく動いたが、すでに美耶子は半睡眼だ。これは、珠子が美耶子を腹話術人形として使っているらしい。
「おう、おやすみ。珠子もいい夢みろよ」
おれは珠子に笑いかけた。どっちにしろ美耶子はもうすでにオヤスミしているので、話しかけてもしょうがない。
美耶子の首がカクンと前後に揺らいだ後、珠子は無表情のまま美耶子を引きずって退出した。双子の二人はひとつの部屋を共用しているのである。
「しかし……なぜ腹話術?」
双子が姿を消すのを見送ってから、おれは首を傾げた。
「珠ちゃんは恥ずかしがり屋だから……」
苑子がわかったよーなわからんよーなことを言う。
まあ、珠子ともちょっとした事件があったからなー。多少なりともおれという存在を意識するようになってきたということか。
それはそれとして。
「残った問題はコレだな」
おれが腕組みしてつぶやくと、苑子も真似をして腕組みをした。
「そうだね」
おれと苑子の二人ぶんの視線の先にはむろん、爆睡中の一子ちゃんの寝姿があったりした。
「しょうがないな。おぶってこう」
「手伝う」
「うむ」
おれはぐったりした一子ちゃんの身体を抱き起こした。
いわゆるシンデレラ抱きというか、お姫さまだっこというのは、実用的ではない。女の子ったって、十五、六にもなればそれなりの重さがある。一子ちゃんが平均より体重があるとは言わないが、それにしたって、腕の力だけで、広い宇多方家を一子ちゃんの部屋まで連れていく――というか運搬する――のは容易ではない。
なので、おんぶが現実的なのである。
よっこいしょ。
寝ている人間はおぶわれているという自覚がないから、かんたんに背負わせてくれない。だが、後ろで苑子がサポートしてくれたので、うまくおぶえた。
むふ。
一子ちゃんのおっぱいが背中に当たっている。
掌も一子ちゃんのヒップを支えるのに大活躍だ。あ、落ちそうだ、支えなきゃ、むぎゅ(握った感触)――もにゅ(戻ってきた感触)。
くうううう。
役得ですか? 役得ですね? 夜更かしさんサイコーッ。
などと思いつつ、顔はそれなりにめんどくさそうに、おれはキィキィ鳴る宇多方家の廊下を歩いた。
耳元には、くーすーという一子ちゃんの穏やかな寝息と、あまい体臭が漂ってきたりしている。側に苑子がいなければ、送り狼になること必然みたいな様相を呈しているが、むろん、おれは紳士だからそんなことはしないぞ。触るだけだ。もみもみ。
やっぱり役得だなあ。
などと思っていると、一子ちゃんの部屋に着いてしまった。くそう。
苑子が先に立ってふすまをあける。ちなみに、この部屋は苑子の部屋でもある。部屋数が足りないわけではない。苑子が一人で寝るのが苦手なためらしい。
調度は多くはない。和風の文机がふたつ。苑子のための本棚、人形やぬいぐるみが飾られたケースつきの衣装箪笥に、三面鏡台(お母さんの形見らしい)などだ。
子供部屋の華やかさや混沌とは無縁のたたずまいである。
「待っててね、いま、お布団敷くから」
苑子が言った。
読みかけの雑誌、しおりがいくつもはさまった文庫本、春物のカーディガン、作りかけとおぼしいドライフラワーの束、近くのスーパーの特売チラシ(クーポン券は切り取り済み)、通信教育の教科書などの、どーやら一子ちゃんが日常に使っているものを苑子が片づけていく。
一子ちゃんの地の性格は、意外にズボラなのかもしれない。今もおれの背中で無防備に寝こけているし。
苑子はてきぱきと部屋を片づけると、二組、布団を敷きはじめる。
真っ白なシーツを広げる。そしてブルーの花柄のタオルケット。
「いいよ、おにいちゃん」
「あいよ」
幾度となく繰り返したコンビネーション。おれたちの息はぴったりだ。
どさ。一子ちゃんを布団の上に転がす。さすがに着替えまではさせていられない。まあ、十二単を着こんでいるわけでもなし、大丈夫でしょう。
廊下に出たおれと苑子は両手をたがいに合わせてハイタッチする。
「ミッションコンプリート」
「お疲れさま」
「じゃあ、苑子も寝ろや。おやすみ」
おれは自室にさがるべく片手をあげた。
おろした手を、苑子の広いおでこに置いて、なでなでした。
眼鏡の奥の苑子は眼が嬉しそうに細まる。
「おやすみ……おにいちゃん」
2001/10/6